今日は「後脛骨筋の機能」について、徹底的に解説していきます。
後脛骨筋は、足部の内側縦アーチを保持するうえで非常に重要な筋肉です。
今回はその解剖学的特徴、機能、歩行時の役割、トレーニング方法まで、網羅的にお伝えします。
まずは解剖と機能、そして個体差についてです。
後脛骨筋は、下腿の骨間膜から起始し、主に舟状骨と内側楔状骨に停止します。
ただし、この停止部には個体差が大きく存在します。
タイプ1〜4Cまで分類されており、舟状骨と内側楔状骨はすべてのタイプで共通して付着しています。
補助的な腱を持つ人もおり、その付着部は外側楔状骨、中足骨、短母趾屈筋、長腓骨筋、第1中足骨、立方骨など多岐にわたります。
つまり、後脛骨筋が内側縦アーチにだけ作用する人もいれば、外側縦アーチや横アーチにまで影響を与える人もいるということです。
後脛骨筋の一般的な作用は、足部の底屈と内がえし、そして内側縦アーチを持ち上げるような機能です。
体表から見た場合、地面に足がついている時には、内側縦アーチを引き上げるイメージになります。
一方、地面から足が離れたOKC(Open Kinetic Chain)の状態では、底屈・内転・内がえしを行う「回外作用」を発揮します。
次に、足部の各関節軸に対する後脛骨筋の作用を整理してみましょう。
後脛骨筋は、足関節軸、距骨下関節軸、横足根関節の斜軸および縦軸の4つすべてに作用します。
各軸において底屈・内転・内がえしを行うため、足部全体を回外方向に強く作用させる代表的な筋肉であることがわかります。
また、下腿に対する作用も重要です。
後脛骨筋は骨間膜に起始しているため、底屈時には腓骨を脛骨に引き寄せるような動きをします。
これにより果間距離が縮まり、足関節の左右方向の不安定性が高まる局面で、後脛骨筋が安定性を補います。
支配神経は脛骨神経で、これは坐骨神経から分岐して下腿後面の筋肉をすべて支配しています。
ここからは歩行中の働きに移ります。
歩行中、後脛骨筋は内側縦アーチを保持し、回外作用を発揮します。
立脚前半では、急激な回内を抑制する「遠心性収縮」が、
立脚後半では、蹴り出しをサポートする「求心性収縮」が起こります。
接地直後は距骨下関節が回内方向に動くため、後脛骨筋はその過剰な回内を抑制します。
これは遠心性収縮による減速作用です。
荷重応答期から立脚中期にかけては、過剰な下腿前傾を防ぎ、
その後、回外と下腿の外旋を加速する求心性収縮へと切り替わります。
さらに、横足根関節の斜軸での回外・底屈・内転を維持し、足部を地面に押し付けるような安定性を確保します。
アーチを高く保持しつつ、距骨以遠の足根骨や中足骨を後内方に維持し、最終的に踵が持ち上がる「ヒールリフト」を支えます。
後脛骨筋に関連する代表的な疾患が「後脛骨筋機能不全」です。
これは成人の後天的扁平足の主な原因のひとつです。
内側組織に繰り返し加わる過負荷や過剰使用により、内果周囲の血流が悪化し、
腱の変性や断裂のリスクが高まります。
特に過剰回内のある足では、こうした機能不全が起こりやすく、
腱が損傷すると重度の扁平足を引き起こし、疼痛や機能障害につながります。
では、どのように後脛骨筋を鍛えるべきでしょうか?
歩行やアーチ保持に重要なこの筋肉を、効果的にトレーニングする方法は「足部の内転運動」です。
踵上げ(ヒールレイズ)や回外運動もありますが、
研究によると、後脛骨筋が最も活性化するのは「純粋な足部の内転運動」です。
片脚での踵上げは見た目ほど後脛骨筋を選択的に鍛えているわけではありません。
したがって、後脛骨筋をターゲットにする場合は、抵抗をかけた足部の内転運動が推奨されます。
まとめです。
後脛骨筋は、舟状骨の底面に付着します。
舟状骨は内側縦アーチの中心に位置する「キーストーン(要石)」であり、
それを支える後脛骨筋は、アーチ維持にとって最重要の筋肉です。
歩行では、立脚前半での遠心性収縮によるブレーキ、
立脚後半での求心性収縮によるアクセル作用、
この両面の働きを持ちます。
機能不全は後天的扁平足の原因になり、進行すると重篤な障害につながるため予防・介入が重要です。
トレーニング方法としては、足部の内転運動がもっとも効果的です。
このように、一つの筋を多角的に理解することで、その臨床的重要性や介入の方向性が明確になります。
本日の内容は以上です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
より深く足部を学びたい方はこちらを見てみてください!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
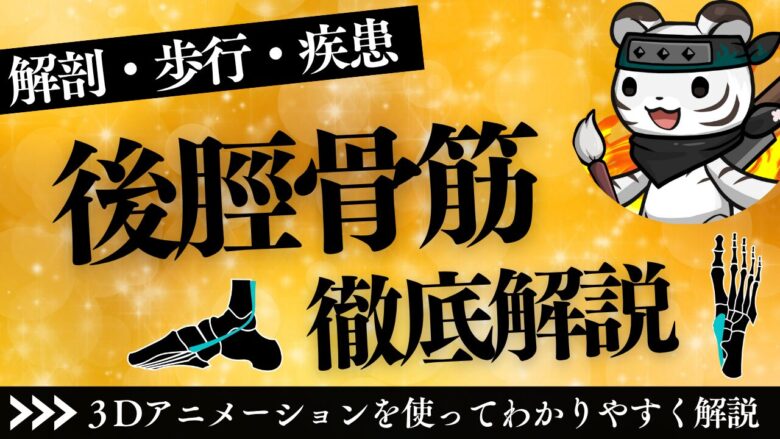
.png)
