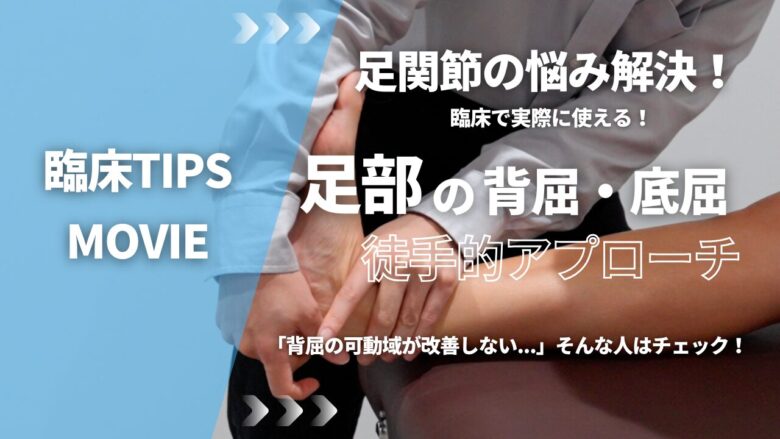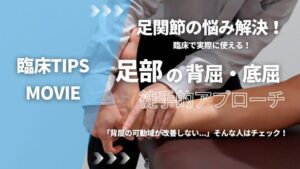「足関節の背屈がなかなか改善しない…」
「底屈も硬い気がするけど、どこを施術すればいいかわからない」
「距骨なのか?脂肪体なのか?評価のポイントが掴めない…」
こんな悩み、臨床で感じたことはありませんか?
足関節は外傷後の機能障害や慢性疾患のリハビリなど、現場で触れる機会がとても多い部位です。
ですが、評価と施術のポイントが整理できていないと、
「とりあえずストレッチ」「なんとなく動かしてみる」…そんなアプローチになってしまいがちです。
新人の頃の私は本当にそんな感じでした・・・
実は、背屈制限が改善しない原因は“後方組織”だけではありません。
距骨後方の硬さやFHL・脂肪体の滑走不良だけでなく、前方組織や底屈制限が影響しているケースも少なくないんです。
今回の動画では、
- 足関節背屈制限の評価手順
- 底屈可動域の重要性と施術ポイント
- 後方組織・前方組織の両面から可動域を改善するアプローチ
これらを実際の評価手順に沿って、わかりやすく解説しています。
「背屈制限の改善に苦戦している」
「距骨や脂肪体までしっかり評価したい」
そんな先生にとって、明日から臨床で試せるヒントが詰まった内容です。
ぜひ最後までチェックしてみてください!
目次
文章でわかる!足関節背屈・底屈アプローチのポイント

動画では評価から施術までを詳しく解説していますが、ここでも要点をシンプルにまとめておきます。
「まず文章でざっくり押さえてから動画を見る」もよし、「動画を見たあと復習用に読む」もよし、どちらにも使える内容です。
1. 足関節背屈制限へのアプローチ
- 後方組織の評価が第一歩→ アキレス腱、脂肪体、長母趾屈筋(FHL)などを中心に可動性をチェック
- 距骨後方の硬さに要注意→ 滑走性が失われると背屈が大きく制限される
- 背屈が改善しない場合は底屈を確認→ 前方組織のタイトネスが隠れた原因になっているケースも多い
2. 足関節底屈制限へのアプローチ
- 底屈可動域が狭い人は要チェック→ 特に足趾屈曲制限との関係に注目
- 硬くなりやすい筋はここ!→ 前脛骨筋、長母趾伸筋、長趾伸筋など
- ストレッチのポイント→踵骨を下方に牽引しながら行うことでより伸張される
- ストレッチ後は必ず背屈を再評価→ 底屈の改善が背屈可動域にもつながる
3. 臨床でのポイント
- 背屈制限は「後方組織」だけ見ていては不十分
- 前方組織や足趾の動きまで含めた“全体評価”が必須
- 評価と施術を繰り返すことで、改善への近道になる
このまとめを頭に入れてから動画を見ると、各アプローチの意図や施術のポイントがさらに理解しやすくなります。
ぜひ、動画と合わせてご活用ください!