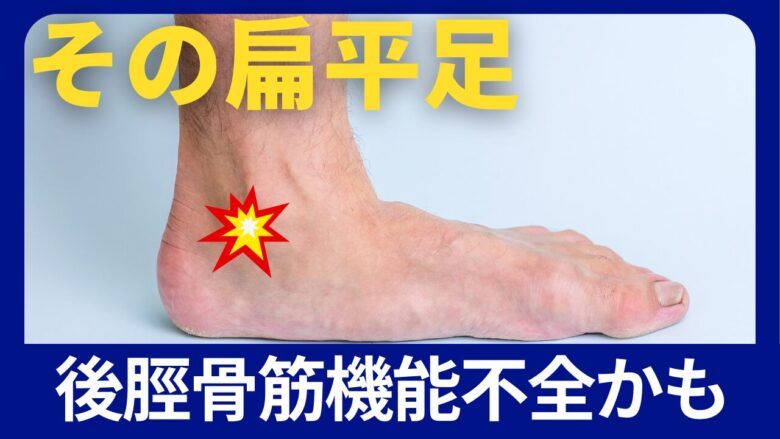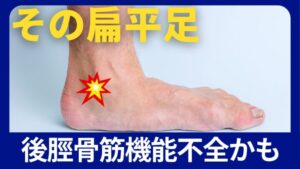「わたし、扁平足なんです。」
患者さんの足をみていると、このセリフはかなり耳にします。
確かに、アーチが潰れ気味、距骨下関節の回内が強い、そんな足の人はたくさんいますよね。
で、その扁平足が何かの問題になっているか。
これは、yesの場合とnoの場合があります。
例えば、子供はみんな扁平足です。
でもほとんどの人は問題ないですよね。
じゃあ、大人はどうでしょうか?
扁平足でも、痛みもなく、生活に不自由したことがない人はたくさんいると思います。
では、どんな扁平足が問題になってくるのでしょうか?
成人の後天的な扁平足の主な原因として知られる後脛骨筋機能不全。
後脛骨筋機能不全は、腱炎から扁平足変形まで、連続体として進行する状態です。
早期診断と治療は、状態の進行とより侵襲的な介入の必要性を防ぐために重要であると言われています。
そして、放置すると、痛み、可動域の制限、歩行障害を引き起こす可能性があります。
どうでしょうか?
この病態を知っていて、早期に適切にアドバイスできることは臨床家にとっては非常に重要なことですよね。
今回は、この後脛骨筋機能不全について、3Dアニメーション動画を用いて解説していきます。
ぜひ最後までお読みください!
後脛骨筋機能不全とは
後脛骨筋機能不全(以下PTTD)は、足の内側の主要な腱である後脛骨筋の炎症や損傷によって引き起こされる状態です。この腱は、足の縦アーチを支え、歩行時に足を内側に回す役割を果たします。PTTDは、腱炎から扁平足変形まで、連続体として進行する状態です。
解剖学的背景
後脛骨筋は、下腿の奥深くにある筋肉で、その腱は内くるぶしの後ろを通って足の裏に伸び、舟状骨、楔状骨、中足骨に付着します。
後脛骨筋は、足の縦アーチの最も重要な動的安定装置であり、歩行中に足部が回内するのを助け、踵を持ち上げる役割も果たします。
後脛骨筋腱は、内くるぶしの周りで特に負荷がかかりやすく、この部位で炎症や変性が起こりやすいです。
後脛骨筋腱には、内くるぶしの後ろを通る部分の血流が乏しいため、損傷からの回復が遅くなる可能性があります
発生要因とリスクファクター
後脛骨筋機能不全の正確な原因は完全には解明されていませんが、多くの要因が複合的に作用していると考えられています。
●加齢: 後脛骨筋腱は、加齢に伴い変性し、弱くなる傾向があります。
●過剰使用: ランニングやジャンプなどの反復動作は、後脛骨筋腱に過剰な負荷をかけ、炎症や損傷を引き起こす可能性があります。
●肥満: 肥満は、後脛骨筋腱を含む足と足首の関節に負担をかけ、PTTDのリスクを高めます。
●扁平足: 扁平足の人は、後脛骨筋腱に過剰なストレスがかかり、PTTDを起こしやすくなります。
●糖尿病: 糖尿病は、後脛骨筋腱を含む体の組織の治癒能力を低下させる可能性があります。
●ステロイドの使用: ステロイド注射は、後脛骨筋腱の断裂のリスクを高める可能性があります。
症状と患者の訴え
PTTDの症状は、状態の進行度合いによって異なります。初期には、内くるぶしの後ろや足の内側に痛みを感じることが多く、活動後に悪化する傾向があります。また、患部が腫れたり、熱を持ったりすることもあります。
状態が進行すると、足のアーチが徐々に崩れて扁平足になり、歩行が困難になることがあります。
患者は、長時間歩いたり立ったりするのが辛い、階段の上り下りが困難、靴が合わなくなったなどを訴えることがあります。
診断
PTTDの診断は、患者の病歴、身体診察、画像検査に基づいて行われます。
●病歴: 医師は、患者の症状、発症時期、活動レベル、過去の病歴などを詳しく聞き取ります。
●身体診察: 医師は、患者の足と足首を触診して、腫れ、熱感、圧痛の有無などを確認します。また、患者の足のアーチの状態、足首の可動域、後脛骨筋の筋力を評価します。
●画像検査:
○X線検査: 足の骨の構造異常や関節炎の有無を評価するために使用されます。
○超音波検査: 後脛骨筋腱の厚さ、構造、炎症の程度を評価するために使用されます。
○MRI検査: 後脛骨筋腱の損傷の程度、周囲の組織の状態、他の病態の有無を評価するために使用されます。
治療
PTTDの治療は、状態の重症度によって異なります。
保存療法: 軽度から中等度のPTTDの場合、保存療法が最初の選択肢となります。
手術療法: 保存療法で効果がない場合や、後脛骨筋腱が断裂している場合は、手術が必要になることがあります。
ここでは、予防的観点から、後脛骨筋を鍛えるトレーニングを紹介します。
すでに診断されている方は、医師の指示のもと運動のパラメータ(負荷の大きさ、回数、セット数、運動期間など)を相談の上実施してください。
まとめ
いかがだったでしょうか?
症状のある扁平足の患者さんに対しては、この後脛骨筋機能不全を頭に入れて関わる必要があります。
また症状がない扁平足の方にも、予防的な観点から、足部のトレーニングを検討しても良いかもしれませんね。
それでは最後までお読みいただきありがとうございました!
後脛骨筋以外にも足部にはたくさんの筋が存在しています。より深く足部の解剖を学びたい方はこちらも確認してみてください!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
参考文献
Bubra PS, Keighley GS, Rateesh S, Carmody D. Posterior tibial tendon dysfunction: An overlooked cause of foot deformity. J Fam Med Prim Care. (2015)
Guelfi M, Pantalone A, Mirapeix RM, Vanni D, Usuelli FG, Guelfi M, Salini V. Anatomy, pathophysiology and classification of posterior tibial tendon dysfunction. Foot Ankle Surg. (2014)
Ling SKK, Lui TH. Posterior tibial tendon dysfunction: An overview. Open Orthop J. (2017)
Mak RYS, Cheng JHM, Chin KH, Chu CY. Pathologies and postoperative features of posterior tibial tendon dysfunction: A pictorial essay. Hong Kong J Radiol. (2024)
Ross MH, Malliaras P, Smith MD, Vicenzino B. The effectiveness of local muscle strengthening exercise in the conservative management of posterior tibial tendon dysfunction: A systematic review and meta-analysis. BMJ Open Sport Exerc Med. (2018)
Ross MH, Smith MD, Vicenzino B. Reported selection criteria for adult acquired flatfoot deformity and posterior tibial tendon dysfunction: Are they one and the same? A systematic review. PLoS ONE. (2017)