こんにちは、PTタイガーです。
本日は「ランニングシューズの4つのパラダイム」というテーマでお話しします。
まず今回参考にしたのは、「ランニングシューズデザインにおける生体力学的トレードオフ」という、ハーバード大学の先生が執筆した論文です。
非常に興味深い内容だったため、2回に分けてご紹介します。
今回は「4つのパラダイム」について、次回は「7つのトレードオフ」について解説する予定です。
さて、「パラダイム」という言葉には、「物事の見方や考え方の枠組み」という意味があります。
かみ砕いて言えば、「私たちが当たり前だと思っている前提やルール」のことです。
たとえば「パラダイムシフト」という言葉がありますが、これは今まで常識だった考え方が、まったく新しい価値観に置き換わる現象を指します。
こうしたパラダイムの変化は、医療の現場でも頻繁に起こっています。
たとえば急性外傷の処置方法について、かつては「RICE処置」が一般的でしたが、現在では「PEACE & LOVE」というアプローチが、より包括的で適切とされています。
このように、医療の世界にも複数のパラダイムが存在し、時代とともに変化していくのです。
そして今回のテーマであるランニングシューズにも、4つの代表的なパラダイムがあるとされています。
以下、それぞれの考え方を紹介していきます。
快適性の最大化
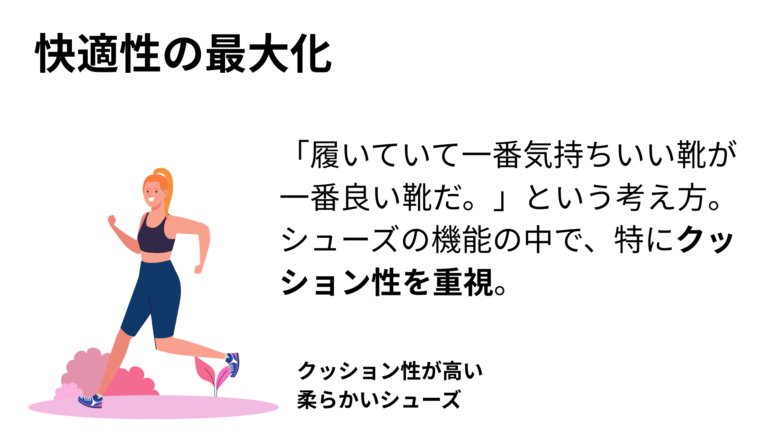
これは「履いていて一番気持ちがいい靴が、最も良い靴である」という考え方です。
クッション性を重視しており、「柔らかさ」こそが最も重要な要素とされます。
この考え方には好みの差がありますが、初心者や、あまり走った経験のない方には特におすすめされる傾向があります。
機能的な弱点の修正・サポート
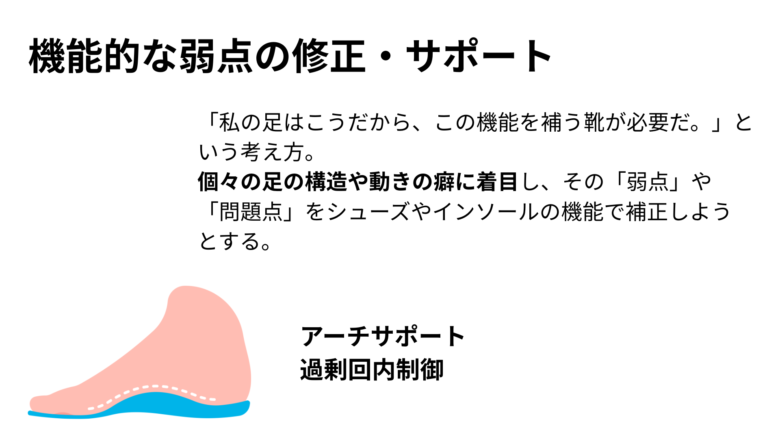
これは、「自分の足に特有の問題を補う靴が必要だ」という視点です。
足の構造や動きの癖に注目し、その弱点をシューズやインソールの機能で補正しようとする考え方です。
医療従事者や靴を提供する側にとっては、比較的スタンダードな視点でもあります。
代表的な例としては、アーチサポートのインソールや、過剰回内を制御する構造のシューズなどが挙げられます。
優先的な動きの経路
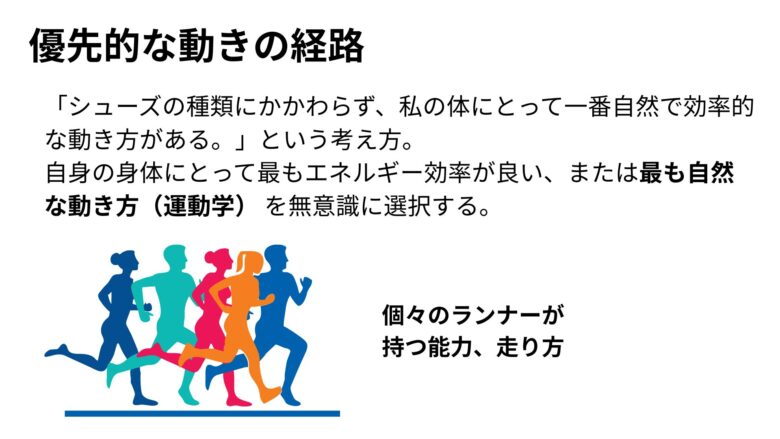
これは「シューズの種類に関係なく、身体にとって自然で効率的な動き方がある」という視点です。
靴そのものよりも、「人」つまり個々のランナーの身体特性に注目する考え方です。
私たちは無意識のうちに、エネルギー効率が最も高く、自然な動作を選択しています。
たとえばピッチ走法(細かい歩幅でテンポよく走る)や、ストライド走法(大きな歩幅で走る)などがあり、脚の長さや身体特性によって適した走法は異なります。
それに合ったシューズを選ぶべきだという考え方です。
自然な状態の奨励
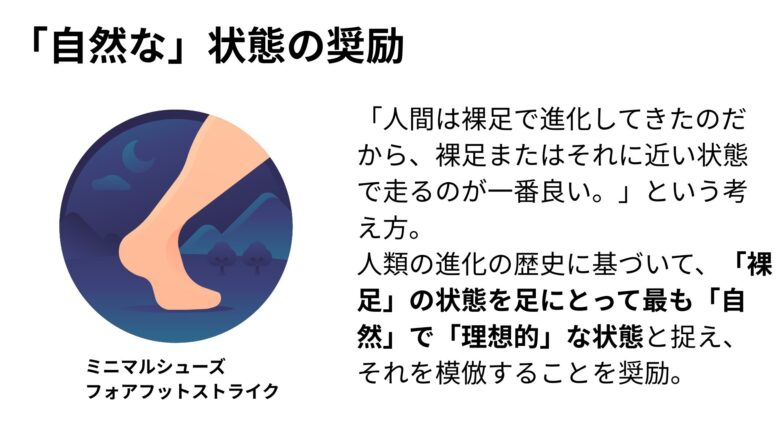
これは「人間は裸足で進化してきたのだから、裸足またはそれに近い状態で走るのが理想的」という考え方です。
人類の進化の歴史に基づき、裸足状態を最も自然で理想的な状態と見なし、それを模倣することを勧めています。
実際に裸足で走る人もいれば、ミニマルシューズやベアフットシューズといった、非常にソールの薄い靴を使う人もいます。
この考え方では、かかとから接地するのではなく、前足部から接地する「フォアフットストライク」が理想とされます。
足部の内在筋が鍛えられるなどのメリットもありますが、現代社会のコンクリートの上を長距離走るには向かないケースもあります。
怪我のリスクもあるため、適用には注意が必要です。
まとめ
このように、ランニングシューズには4つの異なるパラダイムが存在します。
重要なのは、提供者側が「自分の好みや考え方」を自覚したうえで、対象者に合った最適なシューズやインソールを選べるようになることです。
たとえば、提供者自身が「ベアフットこそ理想」と考えていたとしても、脂肪層が薄く硬いかかとを持つ方にそのようなシューズを処方すれば、怪我のリスクが高まります。
だからこそ、自分の信じるパラダイムに固執せず、他の考え方も理解し、対象者のニーズに応じて柔軟に対応することが、専門家としての責任だと私は考えています。
次回は、「7つのトレードオフ」というテーマで、ランニングシューズのバイオメカニクス的な部分をさらに深掘りします。
ぜひ楽しみにしていてください。
それではまた。
より深く足部を学びたい方はこちらを見てみてください!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

.png)
